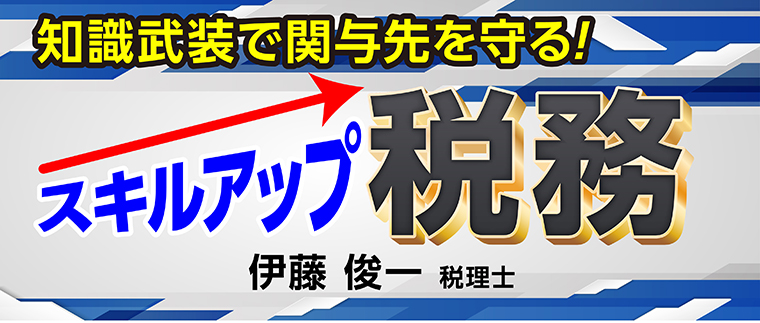社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~57
2025/09/26
これに対し、裁判所は、財産の帰属の判定において、財産の名義が誰であるかは重要な一要素となるが、夫が自己の財産を、自己の扶養する妻名義の預金等の形態で保有するのも珍しいことではなく、また、財産の管理運用を誰がしていたかは重要な一要素となるが、夫婦間においては、妻が夫の財産の管理運用をすることがさほど不自然ではなく、これを殊更重視することはできないのであって、ある財産が誰に帰属するかは、諸般の事情(上記判断事項(1)の①~⑤などの事情と思われます。)を総合考慮して判断する必要があるとしています(上記判断要旨1及び3)。
そうすると、ある財産の管理や運用をその名義人が行っていたとしても、その事実のみをもって課税しないとするのは早計(裏返せば、この事実をもっての課税は、立証不足とみられる可能性もある。)といえます。課税をするかどうかは、他の判定要素を含めて、名義人がその財産を自己の財産として完全に支配管理し自由に処分できる状態にあったかどうか(下記4を参照)で判断することが重要です。
3 財産の名義変更等をなぜその時にしたか(動機)は、財産の帰属の判定において、キーポイントとなる。
本判決では、甲が自己の預金等を乙名義とした動機を、原告らと甲の後妻である乙との関係は険悪であり、かつ、甲と乙との年齢差(17歳)からすると、甲が、自己の死後に乙が金銭的に不自由しないよう自己の財産を乙名義にしておこうと考えていたとしても不自然ではないと認定しています。そして、それを裏付けるように、土地建物の持分については贈与税の申告書を提出しているが、乙名義の預金等については贈与税の申告をしていないこと及び乙が当該預金等を解約して他の用途に使用するなどしたという事情がうかがわれないことから、甲が乙名義の預金等を乙に生前贈与したとは認められないと判断しています(上記判断要旨4~6)。
以上のとおり、本判決では、甲が預金等を乙名義とした動機を、乙名義の預金等の帰属の判定上、重要な要素としていることがうかがわれます(下記4に掲載した判決においても、本判決と同様の観点から、贈与の履行の時期を判断しています。)。
したがって、このような動機がうかがわれ、かつ、財産の名義人がその財産を完全に支配管理し自由に処分できる状態になかったことを推認させるような事実(本件でいえば、乙名義の預金等については、贈与税の申告をしておらず、また、相続開始時まで乙が当該預金等を自己の財産として使用した事実がないこと)があれば、本判決の「乙が乙名義の預金等を管理運用していたとしても、その管理運用は甲の包括的同意あるいはその意向を推しはかってされたもの」と同様の判断がされる可能性は高くなりますし、このような観点からの調査によって収集された証拠は、課税をする上での重要な根拠となり、また、納税者に対する有効な説得材料ともなります。
4 参考となる裁判例
本判決と争点は異なりますが、財産の贈与時期が争われ、本判決と同様の観点から原告が主張する時期に贈与の履行があったとは認められないとした事例(東京地裁平成21年4月24日判決(国側勝訴・原告控訴中))があり、その判示事項については「判決速報(№1155)」で詳しく紹介しています。
この判決では、書面によらない贈与の場合は、「贈与の履行が完了し、受贈者が贈与財産を、自己の財産として完全に支配管理し自由に処分できる状態に至ったときに納税義務が成立する」としています。その上で、①財産(無記名割引債)移転の動機(将来、不測の事態が生じたときに初めて、原告が自由に使用することを許すとの意図)、②財産の支配管理の状況(贈与税の申告の有無、活用状況)、③贈与の履行の動機(本人確認法の施行に伴う贈与の履行)及び④贈与の履行時期(無記名割引債から保護預りへの変化、乗換差金の帰属者の変化)から、原告が贈与財産を、自己の財産として完全に支配管理し自由に処分できるようになったのは、いつであったかを判断しています。
(調査に役立つ基礎知識)
(中略)
1 供述の信用性
実務では、課税に必要な契約書、領収書、通帳やメモ等の物的証拠が十分ではないケースが多く、調査担当者が、納税者はもちろん取引先や従業員あるいは家族などの関係者からの供述等(人的証拠)によって、数少ない物的証拠をつなぎ合わせて課税要件事実を組み立て、課税しているケースが少なくないと思われます。このように、人的証拠である供述(供述証拠)は、時間的に見れば点と点である物的証拠を一連の行為等として結びつけるものであり、重要な証拠といえます。
しかしながら、訴訟上、人的証拠は、一般的に、物的証拠に比べて証拠価値が低いといわれています。なぜなら、人は、思いこみがあったり、間違えたり、忘れたりあるいは嘘をついたりする場合があり、物的証拠に比べその内容が事実と相違している可能性が高いからです。
※伊藤俊一先生の講義は『日税ライブラリー研修』でご受講が可能です。
『日税ライブラリー研修』の詳細・申込はこちら。最新の伊藤先生の研修はこちら。